中学生におすすめの家庭学習教材は?教材の選び方と家庭学習を習慣づけるコツ
2025.12.04 中学生教育PR

中学生になると学習範囲が一気に増加し、学校の授業だけでは置いていかれる可能性があります。高校受験のことを考えると、家庭学習にも時間を割くことも増えるでしょう。難関高校を目指す場合や推薦入試を視野に入れている場合は、中学1年生からしっかりと勉強することも重要です。
しかし、塾に通うのが難しい家庭もあれば、部活動を本格的に頑張りたいという子もいます。小学生の時よりも勉強量が増え、家庭学習のやり方が分からないという子も出てくるでしょう。そこでおすすめなのが、自宅で勉強できる『家庭学習教材(通信教材)』を活用することです。
この記事を読めば、家庭学習教材(通信教材)に関する基本情報から、なぜおすすめなのかの理由についても知ることができます。中学生におすすめの通信教材も紹介していますので、自分の目的に合ったサービスを探してみましょう。
中学生にとって家庭学習が欠かせない理由
まずは、中学生が家庭学習をするべき理由について解説していきます。中学生本人が自覚することも大事ですが、保護者も理解しておくことでサポートしやすくなりますよ。
学習量の増加に伴い、予習・復習しないとついていけない
最も大きい理由は、「小学生と比較して学ぶべき学習量が激増しているから」です。小学生の間は、ほぼすべての授業を先生1人が担当します。しかし、中学生になると各教科・科目で専門の教師が担当するようになります。つまり、各教科・科目の専門性がそれだけ増加するということです。
それに加えて、中学生からは「学習カリキュラムを消化することを最優先」という流れに変わります。分からない生徒がいたとしても、授業自体はどんどん進んでいくのです。分からない部分は授業後に先生に質問したり、家庭学習でしっかりと復習する必要があります。
もし授業スピードについていきたい場合は、あらかじめ予習も済ませておく必要が出てくるでしょう。このように、授業内容をインプットさせるためには復習が、授業の進行速度に追いつくためには予習が必要になるため、中学生からは家庭学習が重要になるのです。
家庭学習の習慣化や時間管理能力が身につく
2つ目の理由は、「勉強のやり方を覚えて学習を習慣化させること」と「時間管理能力・スケジュールの作り方を学ぶこと」ができるからです。
家庭学習の習慣化
勉強することをルーティン化することができれば、勉強に対する印象も大きく変わります。もし中学生のうちに学ぶことを習慣化できれば、今後の人生においても活用することができます。例えば、大学受験や資格試験なども効率良く進めることができるでしょう。
時間管理能力やスケジュールの作り方を学べる
家庭学習を始めようとすると、「時間配分・科目ごとの分量・コンディション・休憩時間」など、さまざまなことを配慮しながらスケジュールを作成することになります。勉強時間は多ければ多いほど良い!というわけではなく、集中できる時間を有効活用する方が重要なのです。
とくに部活動や習い事と両立させたい子にとっては、この時間管理能力は必須と言えるでしょう。大学受験や社会に出てからも非常に役立つ能力です。最初は大雑把でも構いません。自分の力でクリアできそうなスケジュールから組み立ててみましょう。
定期テストや高校受験に向けての準備
学校の授業を真面目に受けたとしても、その内容がすべて定期テストや高校受験に活かされるとは限りません。基本をしっかりと押さえたとしても、応用問題の解き方が分からないと点数は伸びないです。だからこそ、学校で習った内容を家庭学習でレベルアップさせる必要があります。
とくに高校受験に関しては、志望校によって出題傾向・出題難易度が異なります。基礎さえ押さえておけば合格できる可能性がある高校もあれば、中学生で習う公式や文法すべてを駆使しないと合格できない高校もあるのです。そのため、中学3年生になると家庭学習の重要度が上がります。
将来に幅を持たせられる
家庭学習を進めることで、「自分の好きな分野・得意な分野」を見つけることができます。それは将来の夢を固めるのにも役立つのです。将来の夢や職業が固まれば、それに向かって勉強のモチベーションを上げることもできるでしょう。
例えば、数学が好きだと分かれば理数系に強い大学進学を前提とした高校選択ができるようになります。文章を書くのが好きだと分かれば文系に強い高校、プログラミングに興味を持てたのなら情報分野に強い高校など、自分の将来を見据えるためにも家庭学習は必要なのです。
中学生におすすめの家庭学習教材の選び方
続いて、家庭学習を円滑に進めるために教材の選び方を紹介していきます。
自分に合った学習スタイルを選ぶ
まずは、どの学習スタイルで家庭学習を進めたいのか考えてみましょう。各学習スタイルにメリット・デメリットはありますが、個人的には「タブレットスタイル」をおすすめします。
学習スタイル別の特徴
| テキストスタイル | タブレットスタイル | 映像授業 | |
|---|---|---|---|
| テキストの種類 | ・紙ベースのテキスト | ・デジタルテキスト | ・紙ベースのテキスト ・デジタルテキスト |
| 講義動画の有無 | ×(基本的になし) | 〇 | ◎ |
| 費用 | 〇 | △(タブレット代が必要なケースがあるため) | 〇 |
| 質問サポート | 〇 | ◎ | 〇 |
| 添削指導サポート | 〇 | ◎ | △ |
テキストスタイルの強みは、テキストに自由に書き込みできることから「自分だけのオリジナルテキストを作成できる」という点です。費用もそこまで高くなく、多少時間はかかるものの質問サポートや添削指導サポートも用意されています。欠点らしい欠点もありませんが、最近では廃止しているサービスもあります。
最近主流になっているのが、オンラインで学べるタブレットスタイルです。初期費用でタブレット代が請求されるなど、費用面で他の学習スタイルに劣ります。しかし、講義動画を視聴できたり、各種サポートのスピード感も早いなど、品質面での評価は最も優秀です。
映像授業は、プロ講師が教える高品質な授業を視聴できる点が優秀です。何回も見直すことができ、巻き戻しや早送りを使えば効率良く勉強できます。ただし、サポート面に関しては添削指導が付属されていないケースもあります。
定期テスト対策ができる教材を選ぶ
「家庭学習教材=受験対策」というイメージを持っている方も多いですが、必ずしもそういうわけではありません。もちろん、高校受験対策に特化したカリキュラムもありますが、学校の授業を理解するためのカリキュラムもあれば、苦手克服に特化したカリキュラムもあります。
家庭学習教材を選ぶ際には、できるだけ「定期テスト対策」が盛り込まれているものがおすすめです。「定期テスト対策=授業の理解度を深められる」という側面もありますが、内申点対策として定期テストの成績が重要だからです。
無料体験でいくつか教材を試してみる
実際に入会する前に、無料体験を利用してみましょう。できるだけ2~3個ほど候補を挙げ、すべての無料体験を受けた状態で入会する教材を決めることをおすすめします。それによって、以下のようなことを比較できるからです。
- テキストが読みやすく理解しやすいか
- 映像授業を担当している講師と相性が良いか
- タブレットで操作しやすいか
- インターネット環境との相性が良いか
それに加えて、無料体験を受けることでお得に入会できるケースもあります。「初月無料」というケースもあれば、「入会金無料」というケースもあります。全額返金制度を提供していることもあり、こちらであれば10~14日間程度、無料体験という形でサービスを利用できるためおすすめです。
中学生の家庭学習おすすめ教材5選
ここからは、中学生の家庭学習におすすめの教材を5サービス紹介していきます。
家庭学習教材は、入会したタイミングで教材費が異なる場合があります。料金の詳細は、入会前に公式サイトで改めてご確認ください。
スマイルゼミ

| コース | ・標準クラス ・特進クラス |
|---|---|
| 料金 | 中学1年生:8,580円~/月 中学2年生:9,460円~/月 中学3年生:10,340円~/月 |
| 学習スタイル | タブレットスタイル |
| 無料体験 | あり 【無料体験の詳細】 約2週間の無料体験が可能。 実際に入会した際の教材をすべて試すことができる。 |
スマイルゼミは、小学6年生のうちから先取り学習ができる学習教材です。スマイルゼミ会員の中には中間テストから期末テストまでの間に200点近く点数を上げた実績もあり、口コミでの評価も非常に高いものとなっています。月額料金は相場くらいですので、コスパ面で選ぶのもおすすめです。
コースは「標準クラス」と「特進クラス」があり、自分の目的や目標に合わせて選択できます。学校の成績向上や内申点対策なら標準クラス、高校受験対策なら特進クラスがおすすめです。どちらもタブレットで勉強できますので、ちょっとしたスキマ時間で勉強できます。
5教科を24時間学ぶことのできる「Coachez(コーチーズ)」と呼ばれるサービスの導入も始まりました。対話型教材となっていますので、分からないと思った部分をすぐに解消することができます。とくに数学が苦手な方におすすめのサービスと言えるでしょう。
スマイルゼミでは、約2週間、教材がすべてお試しで使える期間があります。タブレットも即発送してくれるので、教材内容や使い勝手など、すべて試すことができるでしょう。
進研ゼミ

| コース | ハイブリッドスタイル/オリジナルスタイル |
|---|---|
| 料金 | 【ハイブリッドスタイル】 中学1年生:6,990円~/月 中学2年生:7,140円~/月 中学3年生:7,190円~/月 【オリジナルスタイル】 中学1年生:6,400円~/月 中学2年生:6,570円~/月 中学3年生:7,090円~/月 |
| 学習スタイル | テキスト(オリジナルスタイル)、タブレット(ハイブリッドスタイル) |
| 無料体験 | あり 【無料体験の詳細】 「わかる」「解ける」を体験できる教材が送られてくる。 期間限定の追加教材プレゼントや有料オプションの資料も受取ることも可能。 |
進研ゼミは、ベネッセコーポレーションが運営している学習教材サービスです。運営実績・歴史・知名度どれを取っても高水準で、圧倒的な信頼性と安全性があります。進研ゼミは小学生というイメージが強いですが、中学準備講座~中学3年生までを対象とした中学講座も提供しています。
学習スタイルは、紙テキストとタブレットを併用した「ハイブリッドスタイル」と、紙テキスト中心で進める「オリジナルスタイル」があります。月額料金にそこまで差はありませんので、ハイブリッドスタイルを選択するケースが多いです。タブレット代に関しても、キャンペーンでお得に購入できます。
定期テストの得点力を上げる独自メソッドを採用していますので、内申点向上を狙っている方にもおすすめします。勉強自体は個別プランで進めてくれるため、部活動との両立もしやすいのも良いですね。高校受験の時期になれば、志望校レベル別の指導を受けられるようにもなります。
料金は入会するタイミングによって異なりますが、だいたい7,000円前後となっており、通信教育サービスの中では少し高め。学習スタイルによる料金差はそこまで大きくありませんので、効率のことも考えてハイブリッドスタイルをおすすめします。
中学ポピー

| コース | ・フル学習コース ・苦手克服コース ・得意をのばすコース |
|---|---|
| 料金 | 中学1年生:4,980円~/月 中学2年生:5,200円~/月 中学3年生:5,400円~/月 |
| 学習スタイル | 紙テキスト・タブレット |
| 無料体験 | なし(資料請求はできる) |
中学ポピーは、紙テキストメインで学習していく学習教材サービスです。「学ぶ力」を身に着けることを目的としており、自学自習を円滑に進められるよう工夫されています。そのため、習い事や部活で忙しくても効率的に勉強できるようになり、それが成績アップにもつながるのです。
学習内容は通っている中学校の教科書準拠ですので、予習・復習がしやすくなっています。1ページあたりの勉強時間も10~30分程度となっており、集中力を保ったまま無理なく続けていける点も嬉しいポイントです。これを繰り返すことで、学習習慣を身に着けることができるでしょう。
最初に紙テキストメインと書きましたが、デジタルサポートとして「デジ・サポ」と呼ばれるサービスもあります。学習進捗と理解度に合わせて学習内容を提案してくれたり、「フル学習コース」や「苦手克服コース」など、自分の目的に合わせて内容を変更することも可能です。
月額料金も5,000円前後となっているため、年単位でも継続しやすい部類に入ります。実技教科も含めた9教科に対応していますので、学習内容とコスパのバランスも良いです。中学3年生になれば受験対策も始められますので、まずは無料資料請求をして内容を確認してみましょう。
スタディサプリ

| コース | ・ベーシックコース |
|---|---|
| 料金 | 1,815円~/月 |
| 学習スタイル | タブレットスタイル |
| 無料体験 | あり 【無料体験の詳細】 申し込みから14日間以内に停止手続きを行えば、料金は一切不要で無料体験を受けられる。 申し込めばすぐに授業を視聴できる。 Webサイトからの申し込み+クレジットカード決済のみという条件あり 公式ホームページ上で各科目の授業を視聴することも可能 |
スタディサプリは、月額1,815円から始められる学習アプリサービスです。定額制なので追加料金が発生することもなく、9教科分の映像授業が受け放題になります。実技4教科にも対応していますので、定期テスト対策・内申点対策として使いやすいサービスと言えるでしょう。
授業自体は1回5分という短さにまとめられており、小さい基礎の部分からしっかりと身に着けることができます。「短時間なのに学習効果ってあるの?」と思われる方もいると思いますが、短時間だからこそ集中して勉強できるのです。それに加えて、短時間の勉強を続けることで学習習慣が身に着きやすくなります。
スタディサプリでは、保護者を対象としたサポート制度も充実しています。とくに気になるのが、「本当に勉強しているのか・本当に理解できているのか」という点です。学習時間・受講講座別の正答率などの進捗メールを定期的に送付してくれますので、監視などのストレスをお子さまに与える心配もありません。
Z会
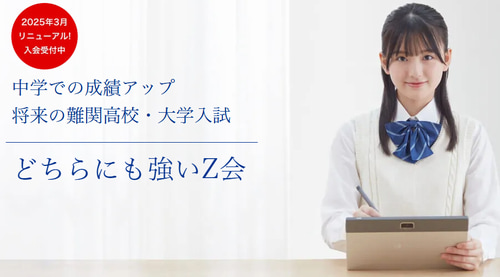
| コース | ・高校受験コース ・中高一貫コース |
|---|---|
| 料金 | 【高校受験コース】 中学1年生:9,470円~/月 中学2年生:11,500円~/月 中学3年生:13,500円~/月 |
| 学習スタイル | タブレットスタイル |
| 無料体験 | あり 【無料体験の詳細】 Web上でタブレット学習の体験ができる 資料請求でお試し教材がもらえる |
Z会は、中学3年分の単元を自由に勉強できる学習教材です。「高校受験コース」と「中高一貫コース」の2種類があり、中学1年生からも先取り学習ができます。料金は中学3年生で13,500円~となっていますので、学習教材の中では少し高めの部類に入りますね。
学習カリキュラムは「要点学習」「問題演習」「単元の総まとめ」で進めていき、基礎の完全定着からさまざまな問題への応用力を身に着けることができます。インプットした知識を練習問題でアウトプットしていきますので、定着度を高めるように
そんなZ会でおすすめしたいポイントは、90年以上の歴史を誇る添削指導です。提出された課題を分析し、一人ひとりに合わせた指導を行っていきます。指導クオリティの高さにも注目ですが、最速当日返却というスピード感も注目です。そのため、「分からない…」という部分をすぐに解決できます。
自分でどのように勉強していけばいいか分からない場合は、「個別強化AIプログラム」の利用もおすすめです。AIが単元ごとに進捗状況と理解度を分析し、「次に取り組むべき問題」を出題してくれます。自分に最適な難易度の問題を出題してくれますので、最短ルートで習得することができます。
中学生の1日の家庭学習時間は平均100分
ここからは、中学生は1日にどのくらい家庭学習しているのか見ていきましょう。
| 勉強時間 | 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 |
|---|---|---|---|
| 0~30分 | 10人 | 7人 | 8人 |
| 30~1時間 | 22人 | 19人 | 8人 |
| 1時間~2時間 | 23人 | 26人 | 10人 |
| 2時間~3時間 | 14人 | 15人 | 14人 |
| 3時間~4時間 | 3人 | 1人 | 9人 |
| 4時間~5時間 | 1人 | – | 5人 |
| 5時間~ | – | 1人 | 3人 |
| 平均勉強時間 | 85.1分 | 87.0分 | 135.3分 |
1年生の勉強時間分布
平均して多かったのが、「30分~1時間」と「1時間~2時間」でした。2時間以上になると塾に通っている子が増え、塾と合計した時間での回答が多かったです。そのため、家庭学習だけに注目すると1~2時間が多い印象があります。
コメントで多かったのは「ご飯やお風呂などを済ませてタブレットやTVを観るため勉強は1時間程度」や「学校以外でも1時間は勉強しておいた方がいいと思うから」というものです。「少なくとも1時間は勉強しておいた方が良さそう…」という意識が強いのも、中学生になったからこそでしょう。
2年生の勉強時間分布
中学2年生も「30~1時間」と「1時間~2時間」が多いことが分かります。中学生の勉強に慣れてきた時期でもあり、宿題だけでなく受験に向けての勉強を始める子も出てくるのが特徴です。塾通いや家庭教師を利用する子も増えていますので、家庭学習だけで考えると1年生と比較してそこまで増えた印象はありません。
コメントでも「塾で1時間ほど勉強して残りは宿題」や「塾と家庭教師にプラスして1時間ほど勉強する」というものが多く見受けられました。中には「漫画の勉強をしている」というコメントもあり、将来に向けて学校の勉強以外にも目を向けている家庭もあるようです。
3年生の勉強時間分布
中学3年生になると、2時間以上勉強する割合がグンと高くなります。やはり高校受験が迫っているのが大きな理由でしょう。それに加えて、3時間以上を選択した子のコメントでは、以下のようなものが多く見受けられました。
- 塾に行って勉強しているが、未だに集中して自宅で勉強することができない
- 塾で2時間40分勉強し、帰宅後に1時間半勉強するようにしている
- 塾で4時間勉強し、帰宅してから2時間は勉強している
3時間以上勉強している子の多くが、塾+自宅学習をしていることが分かります。部活動を引退したことで、学習塾に通う子も増えていますね。難関高校への進学を希望している場合は、毎日4時間以上は勉強しないと難しいのかもしれません。
家庭学習時間は増加傾向にある
上記では中学生の1日の家庭学習時間は平均100分と解説しましたが、2015年の家庭学習時間は平均90分だったのです。これは、『ベネッセ教育総合研究所』が2015年に実施した「第5回学習基本調査」のアンケート結果を元にした結果であり、約10分とはいえ増加しているのが分かります。
| 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | |
|---|---|---|---|
| 宿題 | 57.3分 | 51.3分 | 51.3分 |
| 家庭学習 | 31.2分 | 30分 | 43.9分 |
| 学習塾 | 16.2分 | 21分 | 38.5分 |
| 家庭学習の合計 | 88.5分 | 81.3分 | 95.2分 |
| 全体の合計 | 104.7分 | 102.3分 | 133.7分 |
中学2年生になると、学習塾における勉強時間自体は増えていますが、宿題と家庭学習の勉強時間は減っているのが分かります。全体の勉強時間も最も少ない学年であり、「中学校の学習に慣れてきたから」と予想されています。効率的に宿題を終わらせることができますが、悪く言うと手を抜くことを覚える危険な学年とも言えますね。
中学3年生では、家庭学習と学習塾での勉強時間がグンと増えています。とくに学習塾の割合が2倍近くになっており、受験対策として通い始める子が多いと思われます。部活動引退によって、勉強に時間を割けられるようになったのも理由の一つでしょう。
【重要】1日の平均は100分だが毎日勉強しているわけではない
ここまで中学生の勉強時間について見てきましたが、実際に毎日勉強している中学生は全体の約40%ほどとなっています。最も多かったのは、約3人に2人が回答した「週の半分(4~5日)は勉強している」です。逆に、週の勉強時間が週1以下と答えた子は約5人に1人しかいません。
「最近の子は勉強しないことが多い」と世間では言われていますが、むしろ1週間あたりの勉強日数は増加傾向にあります。しかし、上記でも見て分かる通り毎日勉強している子は半分にも満たないのです。つまり、1週間に1~2日は勉強しない日を作るのも時には必要ということです。
もちろん、勉強が好きな子であれば毎日勉強するのも良いでしょう。しかし、自分の目標や親との約束をクリアしている子に対して「周りは勉強しているのだから毎日勉強しないといけない!」というプレッシャーを与えないようにするべきです。でないと、勉強自体やらなくなってしまいますよ。
中学生が家庭学習を習慣化するためのコツ
最後に、中学生が家庭学習を習慣化させるために始めるコツについて解説していきます。大事なのは、「無理やり勉強を強制しない」ということですよ。
無理なく継続できる範囲内で学習計画を立てる
まずは、「無理なく継続できそうな範囲で学習計画を立てる」というものです。学習計画の作り方は人それぞれありますが、「無理すればクリアできそう…」では長続きしません。
学習計画の目安
| 決め方 | |
|---|---|
| 勉強する期間 | 1ヶ月あたり、1週間あたりなど長いスパンでのまずは計画を考える。 「1ヶ月に15日は家庭学習する」や「1週間の中で平日だけは必ず家庭学習して土日は休む」のような感じで、無理なくクリアできそうな内容にしておく。 |
| 勉強する時間 | 1日あたりにどのくらい勉強するかの時間目安。 「1日合計〇〇分は勉強する!」という決め方でも良いが、「ご飯前に〇分、就寝前に〇分」と綿密に決めた方が分かりやすくておすすめ。 |
| 勉強する教科 | その日にどの教科を勉強するか決める。 「月曜日は国語、火曜日は数学…」でも良いですし、「今週は苦手科目だけを集中して勉強していく」というのでも大丈夫。 |
もし自分だけでは不安な場合は、親御さんも一緒になって考えてあげましょう。学習計画ができるだけ崩れないように、ご飯の時間などを少し調整してあげるのもおすすめです。一緒に学習計画を作ることによって、監視ではなく「見守ること」を意識できるようになります。
集中できる環境を整える
自宅には誘惑されるものが多くあります。テレビやゲーム、漫画、インターネットなどが近くにあると、どうしても集中できないこともあるでしょう。そのため、集中して勉強できるような環境を家族で整えることが重要なのです。ただし、集中できる環境は人によって異なります。
例えば、家族がいる空間で勉強するのが得意な子もいれば、自分だけの静かな空間が得意な子もいます。中には音楽を聴きながら勉強した方が集中できるといった子もいるでしょう。そのため、まずはお子さまとしっかりと話して「どういった環境が集中できるのか」を見極めるのが大事です。
スキマ時間を上手く活用する
中学生になると部活動も始まるため、勉強時間そのものを確保するのが難しくなります。部活動と両立して勉強するためには、ちょっとしたスキマ時間を活用するように工夫してみましょう。
- ご飯ができる前
- お風呂に入る前
- 就寝する前
思い立ったときに勉強するのではなく、ある程度スケジュールを立てておくことをおすすめします。例えば、「夕食前に20分は学校の復習をする」「お風呂が溜まるまでの時間に宿題を終わらせる」「ご飯を食べ終わるまでは休憩時間にして、就寝前の30分で予習する」など、使い方は人それぞれです。
もし電車などで通学している場合は、通学中に勉強するのもおすすめです。ただし、徒歩や自転車に乗っての勉強はNGです。事故に遭う可能性が高くなりますし、周りの人に迷惑をかけてしまいます。自分の足以外で移動している場合にのみ勉強するようにしましょう。